今回のテーマは退職金です。老後の一番の資金となるのが退職金です。しかし退職金は年々減ってきているのが現状です。このようなご時世、退職金は自分で作る時代になってきています。この記事では退職金に不安を抱えている人へ、退職金の準備する手助けとなる情報を発信したいと思います。
そもそも退職金とは?
退職金とは、退職給付制度にて貰えるお金のことを指します。より詳しく説明すると、一定の期間に渡り労働することを条件に退職後に支給される給付であり、この支払いの仕組みは会社毎に定められます。つまり、退職金がいつから貰えるか、そもそも貰えるかは会社毎によって異なります。厚生労働省の調べによると、平成30年の段階で退職給付制度がない会社が20%程度存在するとのことです。今一度、自分の会社の就業規則をきちんと読み返してみましょう。
退職金の種類については、前の記事を参照してください。
記事:確認すべき退職金と老後
今時の退職金の平均
東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和2年版)」より、学校卒業後すぐに入社し、定年まで中小企業で働いた場合、
- 大学卒で約1200万
- 高校卒で約1000万
と言われています。これを聞いて

あと1000万貯めれれば、老後2000万問題は解決だぜ★
と考えた人は甘すぎる!そもそもこんなに貰えると思っている人は少数なのではないでしょうか。
今や会社では退職金を減らそうと躍起になっていますし、退職金を多く貰うためには昇進する必要がありますが、私はこう言いたい。「自分が座れる席は余っていますか?」
退職金、そして老後に対して自助努力を積極的に行うことを検討する必要があります。
退職金を作ろう
退職金が減り、税金が増え続けるこの時代においても、老後に向けて準備する方法はいくつもあります。まずはどんな方法があり、どれが自分に最も合っているのかを考えてみましょう!
①ひたすら貯金

一番リスクが少なく始められて、実感を感じる方法が貯金です。これは「資産を守る」「緊急事態発生時の備え」といった目的も兼ねられますので、ある程度は貯金をしておいたほうがいいです。
ただし、預金の金利はキャンペーン込で高くて0.3%が限界であり、大手の銀行では0.001%だったりします。とてもじゃありませんが増える見込みはほぼありません。そのため給料を増やしつつ、節約して支出を減らし、貯蓄にまわすお金を増やす必要があります。また、別の記事でも書きましたが、貯金はインフレに弱いという側面もあります。
退職金とするには非効率な方法ですので、貯金をしつつ他の方法を同時並行で行ったほうがいいでしょう。
- ペイオフ制度により、1口座1000万円までは確実に守れる安全な方法
- 大金を貯金するには、貯蓄にまわすお金を増やす必要がある(収入UP、支出DOWN)
- インフレに弱い
②個人年金に加入
個人年金とは、保険会社に支払った保険料を積み立て、一定の年齢になったら年金として受け取れる保険の一種です。個人年金には終身や有期年金などの様々なタイプがありますが、最終的にはだいたい110%程度で返ってくるものが多いです。

え。。。少なすぎじゃね?
個人年金の受給額は少ないですが、この保険の真骨頂は節税です。年間の保険料の支払額によって控除される金額は変わりますが、支払額が年間8万円を超えている場合、
- 所得税⇒4万円
- 住民税⇒2.8万円
が控除されます。控除とは、例えて言うと支払った保険料の一部が経費としてみなされ、税金の対象から外されることです。具体的な額で見てみましょう。
例:年収500万の人(所得税率:10%、住民税率:10%)が年間10万を保険料として支払った場合
所得税 ⇒ 4万 × 10% = 0.4万
住民税 ⇒ 2.8万 × 10% = 0.28万
合計 ⇒ 0.4万 + 0.28万 = 0.68万
つまり、年末調整で6800円が戻ってくる計算となります。また、支払いはクレジットカードで払う人が大抵だと思いますので、1%還元とすると1000円分のポイント還元をさらに受けることができます。預金と比較するとかなり優遇されます。
個人年金のデメリットとしては、途中解約すると損(元本割れ)をする可能性が高いこと、外貨建ての場合は為替リスクによっても元本割れが起きる可能性があります(外貨建ての場合、逆にインフレには強いです)。
また、控除額を利回りで計算すると、非常に小さいこともデメリットです。先ほどの例に基づいて利回りを計算してみます。
| 年数 | 保険料の累計合計 | 節税額の合計 | 利回り |
| 1 年目 | ¥10000 | ¥6800 | 6800 / 1 / 10000 × 100 = 6.8% |
| 2 年目 | ¥20000 | ¥13600 | 13600 / 2 / 20000 × 100 = 3.4% |
| 3年目 | ¥30000 | ¥20400 | 20400 / 3 / 30000 × 100 = 2.27% |
| 4 年目 | ¥40000 | ¥27200 | 27200 / 4 / 40000 × 100 = 1.7% |
| 5 年目 | ¥50000 | ¥34000 | 34000 / 5 / 50000 × 100 = 1.36% |
| 6 年目 | ¥60000 | ¥40800 | 40800 / 6 / 60000 × 100 = 1.13% |
| 7 年目 | ¥70000 | ¥47600 | 47600 / 7 / 70000 × 100 = 0.97% |
| 8 年目 | ¥80000 | ¥54400 | 54400 / 8 / 80000 × 100 = 0.85% |
| 9 年目 | ¥90000 | ¥61200 | 61200 / 9 / 90000 × 100 = 0.76% |
| 10 年目 | ¥100000 | ¥68000 | 68000 / 10 / 100000 × 100 = 0.68% |
利回りが低い原因は、控除額がその年だけで完結する、つまり単利だからです。単利・複利についてはまた別の記事でも書きたいと思いますが、中期長期で投資を考える場合、複利効果は絶大です。その複利効果を節税では全く受けることができないため、利回りとしては低くなってしまいます。
- 返戻率は商品によるが、だいたい110%程度
- 個人年金のメインの目的は節税(ただし控除は単利である)
- 途中解約をすると損をする可能性が高い
③iDeCoに参戦
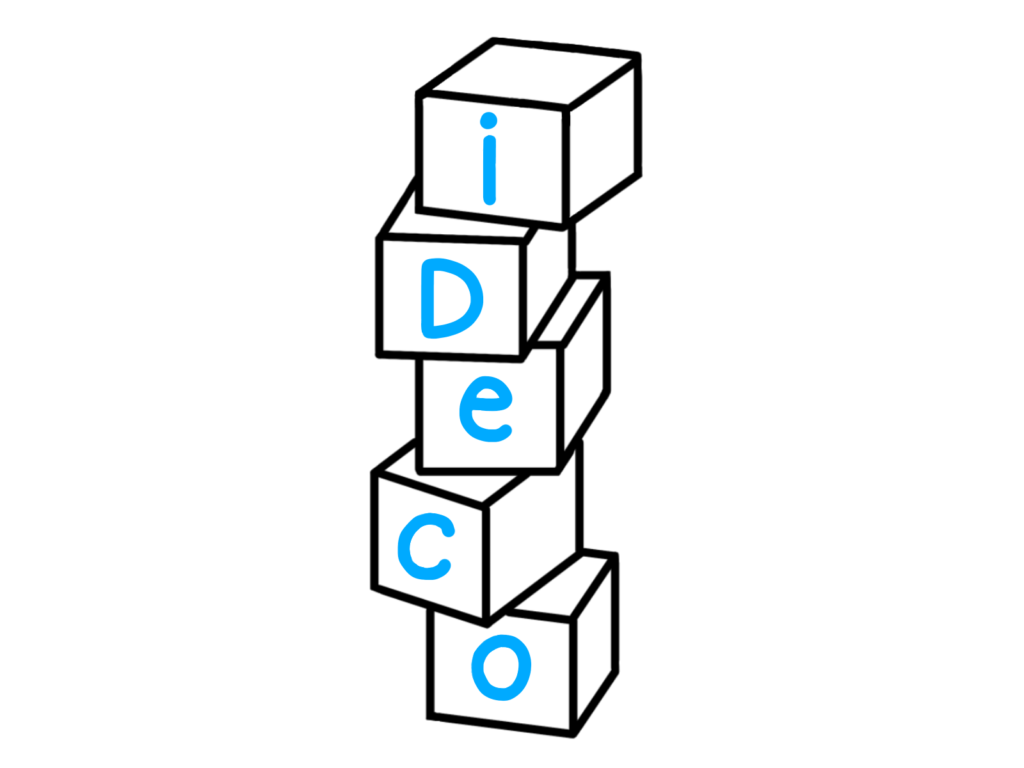
iDeCoとは個人型拠出年金のことであり、「individual-type Defined Contribution pension plan」が由来となっています。簡単に言いますと、毎月自分で決めた支払額(拠出額)を投資として自分で運用する制度のことです。ちなみに企業型拠出年金(DC)は企業が個人に代わって毎月拠出してくれる制度です。
<メリット>
①節税ができる
個人年金と同様、支払ったお金(拠出額)の控除を受けることができます。先ほどの例の場合、個人年金では6.8万円/年が限度でしたが、iDeCoの場合は拠出額全額が控
除の対象となりますので、節税効果はこちらの方が高いです。(こちらも単利ですので、利回りとしては低いです)
②運用益は非課税である
通常、金融商品を利用して資産運用をした場合、運用益に対して税金(源泉分離課税20.315%)がかかりますが、iDeCoを利用した場合はこの税金がかかりません。例を挙げると、運用益として1000万を得た場合、通常は税金として約200万円が引かれてしまいますが、iDeCoの場合はこの税金がかからないことになります。これはかなりの優遇です。
<デメリット>
①損(元本割れ)をする可能性がある
資産運用をするので、運用が上手くいかず、損をしてしまう可能性があります。運用に対する知識を高め、常に情報をキャッチしていく必要があります。ただし、iDeCoは長期運用であることを忘れてはいけません。短期と長期では投資する方向性が全く違います。

長期投資なので、短期的な損益は気にしてはいけないよ!
②受け取る時に税金がかかる
メリット②と矛盾する内容ですが、運用している間は非課税ですが、貰う時に税金がかかります。

訳わからねーよ。。。
何故こんなややこしいシステムにしたのか疑問が残りますが、とにかく貰う時には要注意です。「貰う時に税金かかるなら初めからかけとけよ!」と思うかもしれませんが、抜け道があります。それが退職所得控除です。つまり退職金として貰うことで払う税金を減らすことになります。なお、会社の勤務歴(もしくはiDeCoの使用期間)に応じて控除額が決まりますので、退職金の総額と控除額から
- 退職金とiDeCo全額を一緒に貰う
- iDeCoを半分だけ退職金と一緒に貰い、残りは少しずつ貰い続ける
- 貰う時期をずらす
といった貰い方の中から、どれが一番お得かを考える必要があります。この出口戦略についてはまた別記事で書きたいと思います。
③拠出可能額は人によって異なる
拠出額は自分で決めると書きましたが、その限度額は職種によって異なります。
| 職業 | 拠出限度額 |
| 自営業 | 月6.8万円 |
| 企業型DCがない会社員 | 月2.3万円 |
| 企業型DCがある会社員 | 月2.0万円 |
| 公務員 | 月1.2万円 |
| 無職・専業主夫・主婦 | 月2.3万円 |
もっと掛け金を増やしたい方はNISAなど、別の方法を利用しましょう。
④手数料がかかる
iDeCoは何かと手数料がかかります。
- iDeCoを始めるとき
- 口座管理の手数料
- 他の銀行に移管する時
- 受給する時
この手数料の一部は銀行によって額が異なるので、手数料が少なく、扱っている商品が手厚い銀行を選ぶことが重要となります。
- 節税が出来たり、運用益が非課税であったり、かなり優遇な制度である
- 「元本割れ」「受給時に税金の対象となる」「手数料がかかる」等、注意事項が多い
- 投資、税金、iDeCoに関する知識が必要
パパドラの個人的な意見
自分がやるならiDeCo一択です。私の場合企業型DCに加入しているため始めることが出来ないことを悔しく思っています(正確には、企業側がiDeCoを併用してもいい契約・体制であれば併用可能だが、ハードルが高く、どの企業もほぼ無理)。iDeCo・資産運用・税金の知識があって最大限の効果を発揮しますが、iDeCoほど老後対策に優遇した制度はないと思っています。
また、iDeCoは少しずつ制度が改正されています。
①2022年5月以降、加入年齢の上限が60歳未満⇒65歳未満まで延びる
②2022年10月以降、企業型DCとiDeCoの同時加入のハードルが下がる
老後資金は自助努力が必要となるこの時代、iDeCoを活用するべきか積極的に検討する価値がある制度だと思います。
ちなみに、iDeCoを開設する銀行は、手数料の安さと扱っている金融商品から選びましょう(積立NISAのようにクレジットカードを使用できる金融機関は今のところありません)。オススメはiDeCoの受け取り時、並びに他確定拠出年金等への移換以外に運営管理機関(つまり銀行)への手数料が0円のSBI証券です。ここはNISAや海外株も買えるので、まず失敗することはないと思います。

最後に
私はiDeCoを推していますが、元本割れのリスクがあることを忘れてはいけません。「資産運用なんてできない!」「より確実性を選びたい!」のであれば個人年金の方がいいと思います。つまり、資産の運用に正解はありませんので、きちんと検討し、自分でこれだと思うものを始めてみるべきだと思います。ただし、資産運用に正解はなくても、ぼったくりは存在します。iDeCo口座を開き、金融商品を購入する際は十分に調べてから行いましょう。



コメント